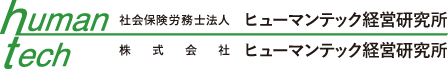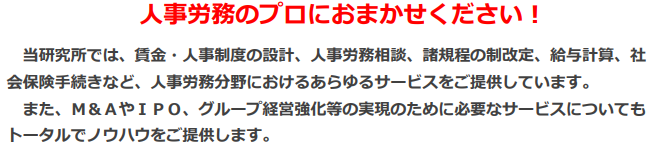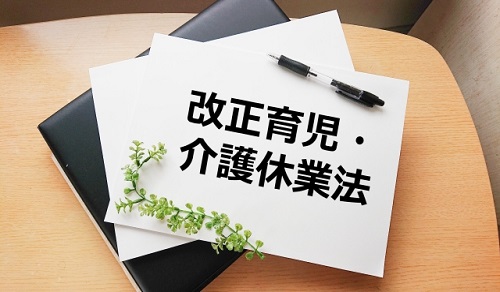2025.04.01
法改正情報
労働基準関係法制研究会報告書の概要(前編) ~ 今後の労基法改正の方向性(総論的課題)について解説! ~
2024年1月より厚生労働省の下で「労働基準関係法制研究会」が立ち上げられ、労働基準法等の改正に向けて包括的かつ中長期的な検討が行われてきましたが、このたび、当研究会より2025年1月8日付で「労働基準関係法制研究会報告書」(以下「報告書」という。)が公表されました。この報告書は、大きく「労働基準関係法制に共通する総論的課題」と「労働時間法制の具体的課題」の2つの章から構成されていますが、今回はこのうち、前者の総論的課題のポイントについて解説していきます。
目次
1.「労働基準関係法制に共通する総論的課題」の3つの論点
「労働基準関係法制に共通する総論的課題」として、次の3つの論点が挙げられています。
| 1. | 労働基準法における「労働者」について |
| 2. | 労働基準法における「事業」について |
| 3. | 労使コミュニケーションのあり方について |
以下、それぞれの内容を見ていきましょう。
2.労働基準法における「労働者」について
労働基準関係法制において保護対象とされる者の範囲は各法律でそれぞれ定められていますが、その中核となるのは、労働基準法における「労働者」です。そこでまず、この「労働者」についてポイントとなる事項を解説していきます。
(1)昭和60年労働基準法研究会報告について
「昭和60年労働基準法研究会報告」では、労働基準法の保護対象となる「労働者」に該当するか否か、すなわち「労働者性」の判断要素がまとめられていますが、公表から現在まで約40年が経過し、働き方の変化・多様化に必ずしも対応できない部分も出てきています。
そこで、具体的な変化・多様化の例として、以下の事項が挙げられています。
| ・ | 産業構造の変化による多種多様な働き方の拡大 | |
| ・ | 新型コロナウイルス感染症まん延を契機としたテレワークの定着による場所にとらわれない働き方の拡大 | |
| ・ | プラットフォーム・エコノミーの進展により、仕事を引き受けるか否かの選択権がありつつも、働き方の実態が「労働者」に近似したプラットフォームワーカー(いわゆる「ギグ・ワーカー」)の世界的拡大 | |
| ・ | AIやアルゴリズムによる労務管理のデジタル化 | |
報告書では、上記の変化・多様化に対応するため、「昭和60年労働基準法研究会報告」公表後の40年で積み重ねられた事例・裁判例等を分析・研究したうえで、本報告の見直しの必要性を検討することが考えられるとしています。また、見直しの議論と並行して、個別の職種について労働者性の判断の参考となるようなガイドライン等を示していくことが考えられるとされています。
とくに、近年拡大するプラットフォームワーカーについては、国際的な動向も視野に入れながら総合的な研究が必要であること等から、労働者性の判断基準に関しては、引き続き専門的な研究の場を設けて総合的な検討を行うべきとされています。
(2)家事使用人について
報告書では、個別の職種で労働基準法適用の課題があるものとして「家事使用人」を挙げています。家事使用人とは、個人宅に出向き、私人と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する者をいい、現行法では、労働基準法の適用が除外されています(労働基準法116条2項)。これは、労働基準法制定当時、家事使用人について住み込みで行われることが多く、当時の適用事業における労働と相当異なっていたことから、同一の労働条件で律することが適当ではないと判断されたことが理由として考えられます。
しかし、現在では、住み込みの使用人として働く家事使用人は減少しており、実質的な働き方は日々就業場所に赴いて、決められた時間業務を遂行する一般的な労働者とほとんど変わらなくなってきており、また、介護サービス事業者の労働者であると同時に家事使用人としても働く者が増えたことなどから、家事使用人のみを特別視して労働基準法を適用除外すべき事情に乏しくなっています。
報告書では、これらの状況を踏まえ、家事使用人に対して労働基準法やそれ以外の労働基準関係法制をどのように適用するかについて、履行確保のあり方も含めた具体的な制度設計の検討に早期に取り組むべきとされています。
3.労働基準法における「事業」について
労働基準法は、「事業(事業場)」を単位として適用されます。そこで、「事業」について報告書の内容を見ていきます。
(1)現行の「事業」について
現行の労働基準法の適用単位である「事業」については、行政解釈上、次の原則が定められています。
| ・ | 工場、鉱山、事務所、店舗等、一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではない | |
| ・ | 一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とする | |
| ・ | 場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う | |
(2)事業場単位の法適用のあり方について
(1)のとおり、現行法で「事業」は場所的概念として捉えられていますが、本研究会に先立って行われた「新しい時代の働き方に関する研究会」では、働き方の多様化やリモートワークの普及等により必ずしも事業場で働かないなど、事業場単位で労働基準法が適用されることが妥当か否かが問題提起されました。
この点について、本研究会では、現時点では引き続き「事業場」単位を原則として維持しつつも、「企業」単位や「複数事業場」単位で同一の労働条件が定められており、適切な労使コミュニケーションが行われるときは、労使の合意により手続きを「企業」単位や「複数事業場」単位で行うことも選択肢になることを明らかにすることが考えられる一方で、テレワーク浸透など場所にとらわれない働き方の広がり等により、「事業」の概念によって規制の対象をとらえることが困難な場合が生じることも予想されるとしています。
これらのことを踏まえ、報告書では、2.(1)で上述した労働者性にかかる研究の場において、あわせて「事業」の概念との関係を含めた議論も行うなど、事業場単位の法適用のあり方について早期に検討に着手する必要があると指摘しています。
4.労使コミュニケーションのあり方について
労働基準法では、労働組合の団体交渉による労働条件の設定や、労使協定の合意による法定基準の調整などの様々な労使コミュニケーションのしくみが採用されています。そこで、最後に、この労使コミュニケーションのあり方について、報告書の内容を見ていきます。
(1)労働組合による労使コミュニケーションについて
報告書では、労働組合法において、個人では不利な立場にある労働者が団結して団体交渉を行うことが保障されていること、労働基準法における労使協定や就業規則の手続きにおいて過半数代表として優先されるのは過半数労働組合であることを踏まえると、労働組合が実質的で効果的な労使コミュニケーションを実現する中核であるとしています。しかし、その一方で、労働組合の推定組織率は2023年では16.3%にとどまり、組織率が長期的に低下しており大きな課題として指摘されています。
このことから、労働組合による労使コミュニケーションを活性化するため、たとえば、過半数労働組合に対して、以下のような支援を行うことができることを明確化していくことが必要とされています。
| ・ | 労働組合が過半数代表として活動する場合の活動時間の確保 | |
| ・ | 使用者からの必要な情報の提供 | |
| ・ | 意見集約のための労働者へのアクセス保障 | |
このほか、報告書では、過半数労働組合と過半数代表者に共通する事項として、労使協定を締結する際等には、過半数代表は事業場の全労働者の代表として意見集約していくべきことも明確化すべきとされています。
(2)過半数代表者による労使コミュニケーションについて
過半数労働組合のない事業場では、過半数代表者を選出したうえで労使協定を締結することとなりますが、事業場において過半数代表者が適切に選出されていない場合があること、選出された過半数代表者が知識、経験および活動に割ける時間の不足により、その役割を果たすことが難しい場合が多いことなど、さまざまな課題が指摘されています。
これらの課題を踏まえ、過半数代表者の選出の適正化や基盤強化のために、以下の事項を法律やガイドライン等で明確にしておくことを検討すべきとされています。
| ・ | 労働基準法における「過半数代表」、その下位概念である「過半数労働組合」、「過半数代表者」の定義 | |
| ・ | 過半数代表者の選出手続 | |
| ・ | 過半数代表者の担う役割および使用者による情報提供や便宜供与 |
|
| ・ | 過半数代表者の権利保護(不利益取扱いを受けないこと等) | |
| ・ | 過半数代表として活動するにあたっての過半数代表者への行政機関等の相談支援 | |
| ・ | 過半数代表者の人数や任期のあり方 | |
5.おわりに
今回は労働基準関係法制研究会報告書における「労働基準関係法制に共通する総論的課題」について解説してきました。今後は、本報告書を踏まえ、来年の労働基準法改正を見据えながら、労働政策審議会において議論が進められる予定となっており、引き続き注視することが必要です。
次回は、本報告書の「労働時間法制の具体的課題」の章における内容について解説していきます。
以上
▽労働基準法の関連コラムをチェックする▽
【2024年4月改正】労働条件明示ルールの変更(前編)~ 無期転換に関する明示ルールの見直し ~
【2024年4月改正】労働条件明示ルールの変更(後編)~ 労働条件の明示事項に新たな項目が追加されます ~
【2024年4月改正】裁量労働制の見直しについてわかりやすく解説(前編)~ 専門業務型裁量労働制の改正内容 ~
【2024年4月改正】裁量労働制の見直しについてわかりやすく解説(後編)~ 企画業務型裁量労働制の改正内容 ~