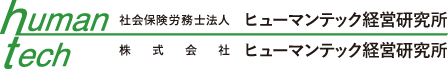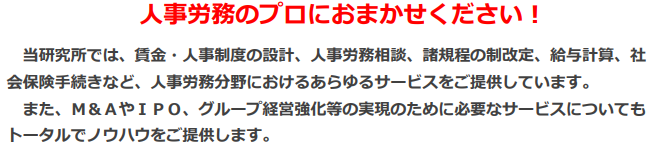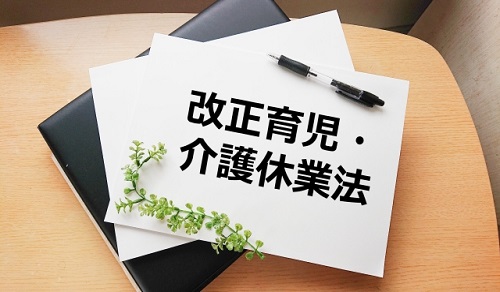2025.03.01
法改正情報
【2025年4月・10月施行】改正育児・介護休業法の実務対応を解説!(育児編) ~ 厚生労働省の『Q&A』をもとに ~
2024年の通常国会で成立した育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法にかかる改正法(※)が2025年4月1日より順次施行される予定です。そこで、改正法の実務的な取扱いについてQ&A形式で解説する厚生労働省の『令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A』(以下「Q&A」という。)の内容を2回にわたって解説します。
今回は育児に関する改正について見ていきます。
※正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」
目次
1. 育児・介護休業法等の育児に関連する改正概要と施行時期
改正育児・介護休業法等の育児に関する改正事項は次のとおりです。
| 育児に関する改正内容 | 施行時期 |
|---|---|
| 子の看護休暇の見直し | 2025年4月1日 |
| 所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大 | |
| 育児短時間勤務の代替措置の追加 | |
| 育児のための在宅勤務等の措置の導入(努力義務) | |
| 300人超の企業に育児休業取得状況の公表の義務づけ | |
| 個別の意向聴取と配慮の義務づけ | 2025年10月1日 |
| 柔軟な働き方を実現するための措置の義務づけ |
2.Q&Aの内容から見る実務対応
では、Q&Aの内容について見ていきましょう。今回は、育児に関する改正のうち、とくに留意点の多い「子の看護休暇の見直し」、「300人超の企業に育児休業取得状況の公表の義務づけ」、「個別の意向聴取と配慮の義務づけ」および「柔軟な働き方を実現するための措置の義務づけ」にかかるQ&Aを一部取り上げて解説します。
なお、以下のQ&Aの内容は、適宜要約して掲載しています。
(1)子の看護休暇の見直し
【Q2-32】
| 子の看護休暇の見直しの内容、とくに新たに取得事由として認められるものはどのようなものか。たとえば、授業参観や運動会に参加する場合でも取得可能か。 |
| 法的には子の看護等休暇の取得事由としては認められないが、法を上回る措置として認めることは可能である。 |
解説
子の看護休暇は、今回の改正により、2025年4月1日以降、名称が「子の看護等休暇」に改称され、対象となる子の範囲が小学校第3学年修了(現行は小学校就学前)まで拡大されるとともに、子の病気、けが、予防接種、健康診断といったこれまでの取得事由に加えて、新たに感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式および卒園式といった事由でも取得が可能となります。
Q&Aでは、授業参観や運動会などの行事に参加する場合について、法的には子の看護等休暇の取得事由として認められないが、法を上回る措置として事業主が独自の判断で取得事由に含めることは差し支えないとされています。
【Q2-33】
| 「小学校第3学年修了までの子」の定義について、就学猶予により、たとえば小学校入学が1年遅れた子に関する子の看護等休暇の取得できる期間は、小学校3年生修了まで(=10 歳になった年度の終わりまで)か。それとも小学校2年生修了まで(=9歳になった年度の終わりまで)か。 |
| 小学校2年生修了までとなる。 |
解説
改正後の子の看護等休暇を取得できる者について、改正育児・介護休業法16条の2では「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」を養育する労働者とされています。このことから、就学猶予を受けて小学校入学が1年遅れた子に関する子の看護等休暇を取得できる労働者は、小学校2年生修了までとなります。
(2)300人超の企業に育児休業取得状況の公表の義務づけ
【Q3-3】
| 育児休業等の取得状況の公表は、毎年いつまでに行えばよいか。 |
| 公表前事業年度終了後、おおむね3ヵ月以内に公表する必要がある。 |
解説
育児休業等の取得状況の公表は、現行法では常時雇用する労働者が1,000人を超える企業に対して義務づけられていますが、改正後は対象企業が拡大され、300人超の企業に義務づけられます。公表にあたっては、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後おおむね3ヵ月以内に行う必要があります。たとえば、事業年度が4月~3月の会社であれば毎年6月末までに公表することが求められます。
なお、具体的な公表事項は下記の①または②のいずれかとされています。
|
① 男性労働者の育児休業等の取得割合
② 男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得割合
|
(3)個別の意向聴取と配慮の義務づけ
【Q2-36】
| 令和3(2021)年改正では、妊娠・出産等の申出時において、すでに「個別の周知・意向確認」が義務づけられていたが、令和6(2024)年改正により、新たに義務づけられた「個別の意向聴取・配慮」とは、何が異なっているのか。 |
| 令和3(2021)年改正の「個別の周知・意向確認」では、育児休業制度等の周知と利用の意向確認に留まっていたのに対し、令和6(2024)年改正により新たに義務づけられた「個別の意向聴取・配慮」では、職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業条件等について個別に聴取し、その意向に配慮することが求められる。 |
解説
「個別の意向聴取・配慮」とは、改正により、現行の個別周知・意向確認に加えて新たに実施することが義務づけられる措置です。
2025年10月1日以降、労働者から、本人または配偶者が妊娠もしくは出産した旨等の申出があった場合に、事業主は、勤務時間や勤務地といった就業条件、仕事と育児の両立支援制度の利用期間の意向を本人から聴取し、その意向に対して、配置や業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、その他の労働条件の見直し等、自社の状況に応じた配慮をしなければならないこととされます。
【Q2-43】
| 聴取した意向について、事業主は具体的にどのように配慮することが考えられるか。また、必ず労働者の希望を叶えなければならないものなのか。 |
| たとえば勤務時間帯や勤務地にかかる配置、業務量、仕事と育児の両立支援制度の利用期間等について配慮することが考えられるが、必ずしも労働者の意向に沿った対応をしなければならないということではない。 |
解説
事業主が行う配慮については、労働者の意向の内容を踏まえた検討を行った結果、何らかの措置を行うか否かは事業主が自社の状況に応じて決定すればよく、必ず労働者の意向に沿った対応をしなければならないということではありません。一方で、Q&Aでは、労働者から聴取した意向に沿った対応が困難な場合には、困難な理由を労働者に説明するなどの丁寧な対応を行うことが重要とされています。
(4)柔軟な働き方を実現するための措置の義務づけ
【Q2-7】
| 事業主が、今回の改正を踏まえ、「柔軟な働き方を実現するための措置」を講ずる際、すでに事業主が独自に当該措置で2つ以上の制度を導入している場合には、特段、新たな対応は求められないという理解でよいか。 |
| すでに導入している制度を「柔軟な働き方を実現するための措置」として講ずることは可能である。 |
解説
3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働けるよう、2025年10月1日以降、時差出勤、テレワーク等の5つの措置のうち、2つ以上の措置を講じることが事業主に義務づけられます。また、措置を選択するにあたっては、事前に過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。この措置について、Q&Aでは、すでに社内で導入している制度を「柔軟な働き方を実現するための措置」として講ずることは可能とされています。ただし、その場合でも、過半数労働組合等からの意見聴取は必要です。また、2つ以上の制度を講じた後、措置内容を追加、変更する場合においても、あらためて過半数労働組合等から意見を聴取する必要があります。
【Q2-7-2】
| 短時間労働者ですでに6時間勤務以下の場合、当該短時間勤務制度の選択肢は措置済みと理解していいか。または、短時間勤務制度以外で2つ以上の措置を実施しなければならないのか。 |
| 短時間勤務制度とそれ以外の措置とあわせて2つ以上講じた場合、措置義務を履行したこととなる。 |
解説
短時間労働者ですでに6時間勤務以下の者も柔軟な働き方を実現するための措置の対象となりますが、そのような労働者がいる場合でも、短時間勤務制度とその他の措置を講じた場合、2つ以上の措置を講じたことになります。
一方、1日の所定労働時間が6時間以下の短時間労働者と6時間を超える正社員がいる場合で、正社員には短時間勤務制度以外の選択肢から2つの措置を講じつつ、短時間労働者には短時間勤務制度を含む2つの措置を講じるような場合は、パートタイム・有期雇用労働法により、下記①~③のうち、その待遇の性質および目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な待遇差に当たらないようにすることが求められます。あわせて、その理由を労働者に対して説明できるようにしておく必要があります。
|
① 職務の内容
② 職務の内容・配置の変更の範囲
③ その他の事情
|
【Q2-11】
| 「テレワーク等」について、月に10日とされているが、3ヵ月で30日にするなど、1年に平均して月10日以上のしくみにしてもよいか。 |
| 平均して「1ヵ月につき10労働日」以上の設定が認められていれば差し支えない。 |
解説
柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢の一つである「テレワーク等」については、①1週間の所定労働日数が5日の労働者については、 1ヵ月につき10労働日以上とし、②1週間の所定労働日数が5日以外の労働者については、①の日数を基準として、1週間の所定労働日数に応じた労働日をテレワーク勤務とすることとされています。この場合、平均して「1ヵ月につき10労働日」以上の設定が認められていればよく、必ずしも毎月10日までの利用とする必要はありません。
【Q2-21-2】
| 「3歳の誕生日の1ヵ月前までの1年間」に該当する第一子を養育する労働者が、 第二子の育児休業中の場合であっても、個別周知・意向確認の実施は必要か。 |
| 実施する必要がある。 |
解説
柔軟な働き方を実現するための措置の選択に資するよう、2025年10月1日以降、労働者の子が3歳の誕生日の1ヵ月前までの1年間に、柔軟な働き方を実現するための措置の内容等について個別周知・意向確認・意向聴取・配慮を実施することが新たに事業主に義務づけられます。これらの事項については、該当する子以外の子の年齢や労働者の育児休業の取得状況等にかかわらず、事業主と労働者がコミュニケーションを取りやすいタイミングを工夫するなどして、当該1年間のいずれかの時期に実施する必要があります。
3.おわりに
今回は、『令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A』から育児に関連する内容の一部を見てきました。Q&Aの内容を理解し、柔軟な働き方を実現するための措置や個別の意向聴取などの具体的な実務対応についてあらためて確認をしておくことが重要です。
次回は、Q&Aの介護に関連する改正内容について見ていきます。
以上
▽改正育児・介護休業法の関連コラムをチェックする▽
【2025年(令和7年)4月・10月施行!】育児・介護休業法等の改正の概要~ 「育児」に関する改正ポイントについて ~
【2025年(令和7年)4月・10月施行!】育児・介護休業法等の改正の概要~ 「介護」・「次世代法」に関する改正ポイントについて ~
【2025年4月施行】出生後休業支援給付金の概要~改正雇用保険法・新たな育児関連給付の創設(前編) ~
【2025年4月施行】育児時短就業給付金の概要~改正雇用保険法・新たな育児関連給付の創設(後編) ~
【法改正対応!】2025年(令和7年)4月施行 主な法改正事項について(前編)~育児・介護休業法の法改正まとめ ~