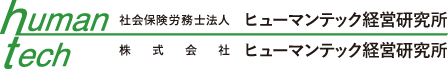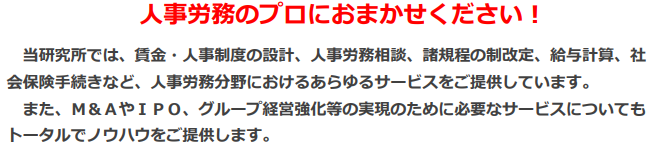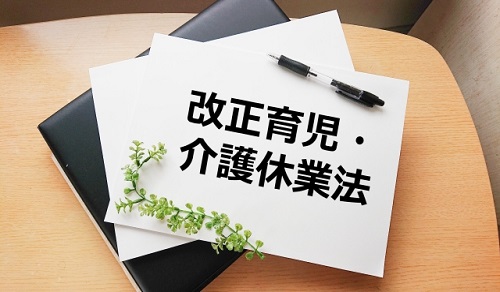2025.01.15
法改正情報
【2025年(令和7年)4月改正】改正次世代法の概要(後編) ~ 改正指針から見る状況把握と数値目標設定のポイント ~
次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)が改正され、2025年4月1日から施行されます。前回は次世代法と施行規則(以下「省令」)の改正内容について見ましたが、今回は同法に基づく行動計画策定指針(以下「指針」)の改正内容から、新たに事業主に義務づけられた一般事業主行動計画策定時の状況把握および数値目標設定におけるポイントを解説していきます。なお、改正指針は、改正法および改正省令と同様、2025年4月1日から適用されます。
▽前回コラムをチェックする▽
【2025年(令和7年)4月改正】改正次世代法の概要(前編)~ 改正の概要とくるみん認定の認定基準見直しのポイント ~
目次
1.状況把握のポイントについて
まずは、新たに義務づけられた状況把握におけるポイントについて、改正された指針の内容を見ていきます。
(1)把握する事項
前回見たとおり、改正法施行後は、一般事業主行動計画(以下「行動計画」)策定時に自社の状況把握をする必要があります。
男女とも仕事と子育てを両立できる職場を目指すためには、育児休業等の利用状況の男女間の格差および長時間労働の改善が必要であることから、把握する事項は直近の事業年度における以下の①および②とされています(詳細は【2025年(令和7年)4月改正】改正次世代法の概要(前編)~改正の概要とくるみん認定の認定基準見直しのポイント~参照)。
【把握が義務づけられる事項】
|
① 男性労働者の「育児休業等取得率」または男性労働者の「育児休業等および育児目的休暇の取得率」の状況(以下「育児休業等の取得の状況」という。)
② フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働および休日労働の合計時間数等の労働時間の状況(以下「労働時間の状況」という。)
|
(2)状況把握後の分析方法
前回見たとおり、改正法施行後は、状況把握を行うとともに、改善すべき事情について適切な方法により分析したうえで、その結果を勘案して行動計画を定めなければならないこととされます。指針では、この状況把握後の分析方法について、自社の課題を分析するうえでの「観点」と課題を改善するための「取組み」という2つの視点から具体例が挙げられています。
【「育児休業等の取得の状況」における分析方法の具体例】
| 分析の観点例 | 取組例(一部抜粋) |
|---|---|
|
□男女がともに育児休業、育児目的休暇等を取得できる状況にあるか。希望どおりの期間が取得できる状況にあるか。
□男性労働者が希望どおりに育児休業等を取得できる職場風土であるか。また、職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土となっているか。
□周囲に気兼ねなく育児休業等を取得できるよう、業務体制の見直しや代替業務に対応する体制の整備等が行われているか。
□育児休業の取得や取得した期間、子育て期間中の時間制約が、評価・登用において不利になっていないか。
|
○定期的な労働者の意識調査(職場風土に関するもの)の実施と改善策の実行
○職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土づくりに向けた意識啓発
○企業トップによる仕事と子育ての両立支援の推進に向けたメッセージの発信
○育児休業制度および出生時育児休業制度の個別周知・意向確認の徹底状況
○仕事と子育ての両立の推進、必要な業務体制および働き方の見直し等に関する管理職を対象とした研修・説明会の実施
○ 育児休業等の取得が中長期的に不利とならないような人事評価制度や運用等の見直しの実施
○育児休業取得者の代替業務に対応する労働者(業務代替者)の確保、業務代替者への手当(賃金の増額)等の検討・実施 など
|
【「労働時間の状況」における分析方法の具体例】
| 分析の観点例 | 取組例(一部抜粋) |
|---|---|
|
□長時間労働ゆえに仕事と家庭の両立が困難となっていないか。また、子育てを行う労働者のみならず、すべての労働者について長時間労働になっていないか。
□長時間労働が、個々の職場だけでなく、組織全体の問題として対応されているか。
|
○組織のトップからの長時間労働是正に関する強いメッセージの発信
○組織全体・部署ごとの数値目標の設定と徹底的なフォローアップ
○組織のトップの会議での部署ごとの残業時間数等の公開・評価の実施
○残業が一定時間数を超える場合の本人と上司に対する通知・指導等 など
|
|
□長時間労働の背景として、長時間労働自体が努力の証として評価されたり、時間当たりの生産性よりも、期間当たりのアウトプットの量によって評価されたりするような職場風土・評価制度になっていないか。
|
○時間当たりの労働生産性を重視した人事評価
○管理職の人事評価における長時間労働是正・生産性向上に関する評価
○帰りやすい職場風土等に向けた管理職自身の勤務時間管理の徹底 など
|
|
□特定の部署・特定の担当者・特定の時期に、特に長時間労働となっていないか。
□必要なときに休みが取れる職場になっているか。
|
○部署横断的な人員配置の見直しを行いうる職位の高い責任者の指名と不断の人員配置の見直し
○属人的な業務体制の見直し・複数担当制や、労働者の「多能工化」による業務のカバー体制の構築 など
|
|
□生産性の高い働き方の実現に向け、業務の優先順位や、業務プロセス等の見直しに対して、管理職等のマネジメントが的確になされているか。
|
○管理職の長時間労働是正に向けたマネジメント力の強化のための研修
○チーム内の業務状況の情報共有/上司による業務の優先順位づけや業務分担の見直し等のマネジメントの徹底 など
|
2.数値目標設定のポイント
次に、数値目標設定のポイントについて見ていきます。
(1)必ず数値目標の設定が必要な事項についての留意点
前回見たとおり、改正法施行後は、行動計画策定時に、育児休業等の取得の状況および労働時間の状況(1.(1)①および② )にかかる数値目標の設定をする必要があります。この数値目標設定の留意点について、指針で示されている要旨は以下のとおりです。
【育児休業等の取得の状況や労働時間の状況にかかる数値目標の設定】
|
・「育児休業等の取得の状況」および「労働時間の状況」にかかる数値目標を設定する必要がある。
・「育児休業等の取得の状況」にかかる数値目標を設定する際には、男女間の著しい育児休業の取得状況の差を勘案し、労働者の取得実績や取得希望等を踏まえて、男性の育児休業取得期間に関する適切な目標が設定されることが望ましい。
・数値目標については、実数、割合、倍数等数値を用いるものであればいずれでもよい。
・数値目標の水準については、計画期間内に達成を目指すものとして、各事業主の実情に見合った水準とすることが重要である。
|
(2)任意で目標を設定する場合の留意点
他方、数値目標設定が義務づけられている項目以外の目標を設定する場合の留意点については、以下のとおり示されています。
【育児休業等の取得の状況や労働時間の状況以外に関する目標の設定】
|
・各企業の実情に応じ、可能な限り定量的な目標とする等、その達成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましい。
・目標の設定にあたっては、くるみん等の認定制度において成果に関する具体的な目標を定めて講じることとされている以下のア~ウの項目を参考にすることも考えられる。
ア 男性労働者の育児休業取得期間の延伸
イ 年次有給休暇の取得促進
ウ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件整備のための措置
・「両立指標に関する指針」(平15.4.8雇児発0408001号)を活用することも効果的であるとともに、同指針による評価の結果を目標として定めることも考えられる。
|
(3)数値目標の達成状況等の点検
行動計画の推進にあたっては、数値目標の達成状況や計画の実施状況の点検が重要です。これらについて、指針で示されている事項は、以下のとおりです。
【計画の実施状況の点検】
|
・行動計画の推進にあたっては、数値目標の達成状況や計画の実施状況の点検・評価を実施し、その結果をその後の対策や計画に反映させる、「計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCA サイクル)」を確立することが重要。
・状況把握・課題分析や、それを踏まえて設定される数値目標についても、併せて点検・評価を行うことが効果的である。
・PDCAサイクルの中で、実効性のある対策の実施や計画の見直し等を行うことを通じて、くるみんやプラチナくるみん等の認定を取得することが期待できる。
|
3.おわりに
今回は次世代法の改正指針の内容について見てきました。2025年4月以降に新たに義務づけられる状況把握や数値目標設定について、指針に記載されたポイントを踏まえたうえで、早めに準備を進めておくことが肝要です。
以上
▽改正雇用保険法の関連コラムをチェックする▽
【2024年(令和6年)5月成立!】改正雇用保険法のポイント
【2025年(令和7年)4月施行】改正雇用保険法・新たな育児関連給付の創設~ 出生後休業支援給付金の概要 ~
▽改正育児・介護休業法の関連コラムをチェックする▽
【【2025年(令和7年)4月・10月施行!】育児・介護休業法等の改正の概要~ 「育児」に関する改正ポイントについて ~