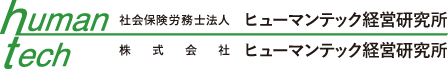2019.06.01
法改正情報
フレックスタイム制の主な改正ポイント
2019年4月から働き方改革関連法が順次施行されています。今回は、改正労働基準法のうち、フレックスタイム制の主な改正ポイントについて見ていきたいと思います。
1.清算期間の上限延長
フレックスタイム制とは、就業規則および労使協定に始業および終業の時刻を従業員本人の決定に委ねる旨を定めた場合に、一定の期間について、週を平均して40時間まで労働させることができる制度です。この一定の期間のことを「清算期間」といいます。
通常、1日8時間、週40時間を超えて労働させた場合には時間外労働となりますが、フレックスタイム制を導入した場合には、1日や1週の労働時間の長さにかかわらず、清算期間を通じて週平均40時間を超えない限り時間外労働とはなりません。したがって、たとえば、ある日に12時間労働させたり、ある週に50時間労働させた場合であっても、清算期間を通じて週平均40時間以内であれば時間外労働とはならず割増賃金を支払う必要はありません。
従来まで、この清算期間の上限は1ヵ月とされていましたが、今回の改正により3ヵ月まで延長されたため、最大3ヵ月の範囲内で労働時間を調整することが可能となりました。
それでは、この点についてもう少し詳しく見てみましょう。
(1)清算期間が1ヵ月を超える場合の割増賃金等の精算について
フレックスタイム制を導入する場合、一般に、清算期間は、給与計算期間が20日締めの会社であれば毎月21日から翌月20日までの1ヵ月、末締めの会社であれば毎月1日から末日までの1ヵ月というように、給与計算期間に合わせている会社がほとんどです。
この場合、これまでは、実際の労働時間が法定労働時間を超過した場合、割増賃金の支払いは1ヵ月単位で行う必要がありましたが、改正法で清算期間が延長されたことにより、最大3ヵ月ごとに割増賃金を支払えばよいこととなりました。一方、従業員にとってもこれまでより長いスパンで労働時間を調整することができるようになりました。
(2)清算期間が1ヵ月を超える場合の過重労働防止措置について
しかし、清算期間が長くなることによって、繁忙月の労働時間が過度に長くなってしまう可能性があります。このため、改正法では過重労働防止の観点から、清算期間が1ヵ月を超える場合には、3ヵ月ごとに支払う時間外労働割増賃金のほかに、その清算期間を1ヵ月ごとに区分した各期間について、週平均労働時間が50時間を超えた時間についての割増賃金を支払わなければならないこととされました。
たとえば、清算期間を4月から3ヵ月ずつに区分することとした場合、4月と5月は、それぞれ週平均50時間を超過した時間について各月の時間外労働として割増賃金を支払い、最終月である6月は週平均50時間を超える時間のほか、4月から6月までの3ヵ月の総実労働時間のうち法定労働時間の総枠を超えた時間から、すでに4月と5月に割増賃金を支払った週平均50時間超過分を差し引いた時間について、割増賃金を支払うこととなります。
2.導入時の手続きにかかる改正
次に、フレックスタイム制を導入する際の手続きの変更点について見てみましょう。
フレックスタイム制の導入にあたっては、就業規則等に定めをするとともに労使協定を締結する必要がありますが、従来までは、この労使協定は届出の義務がありませんでした。今回の改正では、清算期間が1ヵ月を超える場合、所轄労働基準監督署長への届出が義務づけられることとなりましたので注意が必要です。
なお、清算期間の長さは、労使協定にあらかじめ明記しておけば、協定の締結単位である同一事業場内であっても対象者や部署ごとに異なる期間を設定することができますので、導入にあたっては、この点も踏まえて検討するとよいでしょう。
3.さいごに
以上、本年4月1日施行のフレックスタイム制の主な改正点について見てきました。
フレックスタイム制は、一般に、給与計算が複雑になったり従業員との意思疎通が困難になるなどのデメリットがあると言われていますが、その一方で、従業員が通勤ラッシュを回避したり、子育てや通院、資格取得などのために時間を効率的に使うことで、業務の効率化や人材の確保・定着につながるといったメリットも考えられます。
今回の改正で清算期間が1ヵ月から3ヵ月に延長されたことによって、従業員はこれまで以上に柔軟な働き方を選択することができるようになったわけですが、企業にとっては、よりいっそう労働時間の正確な管理や複雑な給与計算などきめ細やかな対応が求められます。導入や運用の見直しを検討する場合は、前述のポイントを含め、制度の全体像をしっかりと理解しておくことが大切です。
ヒューマンテック経営研究所
所長 藤原伸吾(特定社会保険労務士)
※本コラムは、「日経トップリーダー」経営者クラブ『トップの情報CD』(2019年6月号、日経BP発行)での出講内容を一部編集したものです。